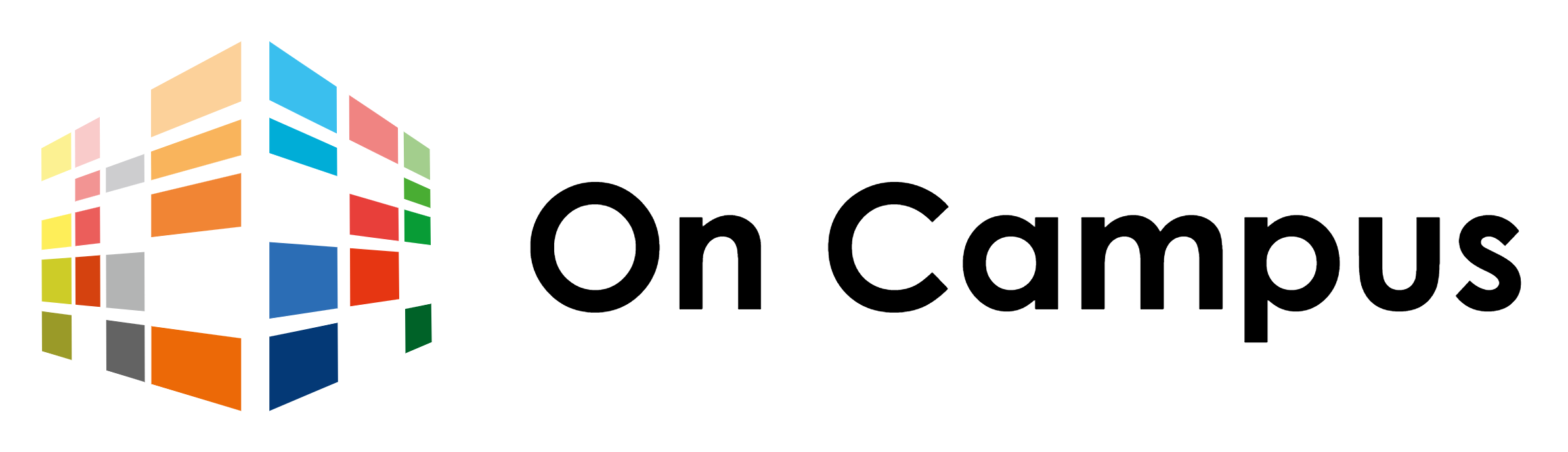シンガポールの南洋理工大学(NTUシンガポール)の科学者たちは、脳からヒントを得たアプローチを用いて、ロボットが痛みを認識し、損傷したときに自己修復する人工知能(AI)を持つ方法を開発しました。
このシステムには、物理的な力によって加えられた圧力から生じる「痛み」を処理して反応するAI対応のセンサーノードがあります。また、軽度の「怪我」の際には、人間の介入を必要とせず、ロボット自身の損傷を検知して修復することができる。
現在、ロボットはセンサーのネットワークを利用して、身近な環境に関する情報を生成している。例えば、災害救助ロボットは、カメラとマイクのセンサーを使って瓦礫の下にいる生存者の位置を特定し、腕のタッチセンサーからの誘導でその人を(がれきの下から)引きずり出す。組立ラインで作業する工場ロボットは、映像を用いてアームを正しい位置に誘導し、タッチセンサーを使って対象物を拾ったときに滑っていないかどうかを判断する。
今日のセンサーは通常、情報を処理するのではなく、学習が行われる単一の大規模で強力な中央処理装置に情報を送る。その結果、既存のロボットは通常重く配線されているため、応答時間が遅れてしまいます。また、損傷の影響を受けやすく、メンテナンスや修理が必要となり、長期に渡って費用がかかる可能性がある。
新しいNTUのアプローチでは、AIをセンサノードのネットワークに埋め込み、複数の小型で低消費電力の処理ユニットに接続して、ロボットの皮膚上に分散した「ミニ脳」のような役割を果たす。これにより、学習は局所的に行われ、従来のロボットと比較して、ロボットに必要な配線や応答時間が5~10倍に短縮されると科学者らは述べている。
このシステムと自己修復性のあるイオンゲル材料を組み合わせることで、ロボットが損傷しても、人の手を介さずに機械的な機能を回復させることができる。
NTUの科学者による画期的な研究は、8月に査読付き科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載された。
この研究の共同執筆者である電気電子工学部のArindam Basu准教授は、「ロボットがいつか人間と一緒に働くようになるためには、彼らが人間と安全に相互作用できるようにするにはどうすればよいかということが一つの関心事です。そのため、世界中の科学者たちは、痛みを『感じる』ことができたり、痛みに反応したり、過酷な動作条件に耐えられるようになったりと、ロボットに意識を持たせる方法を模索してきました。しかし、必要とされる多数のセンサーをまとめることの複雑さと、その結果として生じるシステムの脆弱性が、広く普及するための大きな障壁となっています。」と話す。
ニューロモーフィック・コンピューティングの専門家であるBasu准教授は、「我々の研究は、最小限の配線と回路で効率的に情報処理を行うことができるロボットシステムの実現可能性を実証した。必要な電子部品の数を減らすことで、私たちのシステムは手頃な価格で拡張可能になるはずです。これは、市場での新世代ロボットの採用を加速させるのに役立つでしょう。」と述べている。